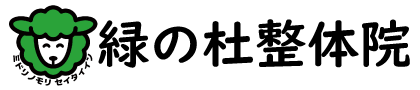ダイエットを成功させたいけど、なかなか結果が出ない…そんなあなたに朗報です。この記事では、減量を加速させるプロテインの活用術を徹底解説!プロテインが減量に効果的なメカニズムから、最適な種類、効果的な摂取タイミングと回数、1日の摂取量、注意点、そして美味しいプロテインレシピまで、網羅的にご紹介します。
ダイエットを成功させたいけど、なかなか結果が出ない…そんなあなたに朗報です。この記事では、減量を加速させるプロテインの活用術を徹底解説!プロテインが減量に効果的なメカニズムから、最適な種類、効果的な摂取タイミングと回数、1日の摂取量、注意点、そして美味しいプロテインレシピまで、網羅的にご紹介します。この記事を読めば、プロテインを正しく理解し、効率的に減量を進めるための知識が身につきます。もう無駄な遠回りは不要です。理想の体型を手に入れるための第一歩を、プロテインと共に踏み出しましょう。具体的な内容としては、ホエイ、ソイ、カゼインといった主要なプロテインの種類ごとの特徴やメリット・デメリットを比較検討し、自分に合ったプロテイン選びをサポート。さらに、トレーニングや食事との効果的な組み合わせ方や、よくある疑問にもお答えします。この記事で、あなたもプロテインマスターになり、健康的に理想の体型を目指しましょう!
1. プロテインで減量できるメカニズム
ダイエットを成功させるためには、ただ摂取カロリーを減らすだけでなく、効率的に体脂肪を燃焼させることが重要です。そこで注目されるのがプロテインの活用です。プロテインは、筋肉の維持・増強に役立つだけでなく、減量にも効果を発揮します。そのメカニズムを詳しく見ていきましょう。
1.1 筋肉と代謝の関係
私たちの体は、常にエネルギーを消費しています。このエネルギー消費のことを代謝といいます。代謝には、基礎代謝、活動代謝、食事誘発性熱産生があります。中でも基礎代謝は、生命維持のために消費されるエネルギーで、全体の約60~70%を占めています。
そして、この基礎代謝を高める鍵となるのが筋肉量です。筋肉は、脂肪よりも多くのエネルギーを消費するため、筋肉量が多いほど基礎代謝が高くなり、痩せやすい体質になります。つまり、筋肉量を増やすことで、より多くのカロリーを消費できるようになり、効率的に減量できるのです。
1.2 プロテインが減量に効果的な理由
プロテインは、筋肉の構成成分であるアミノ酸を豊富に含んでいます。そのため、プロテインを摂取することで、筋肉の合成が促進され、筋肉量の増加につながります。筋肉量が増加すれば基礎代謝が向上し、脂肪燃焼効果も高まります。
また、プロテインには、食欲を抑える効果もあると言われています。プロテインは、消化吸収に時間がかかるため、満腹感を持続させやすく、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。さらに、プロテインは、体内で熱を産生する作用があるため、食事誘発性熱産生を高め、消費カロリーを増やす効果も期待できます。
| 効果 | メカニズム |
|---|---|
| 基礎代謝向上 | 筋肉の構成成分であるアミノ酸を供給し、筋肉量増加を促進。筋肉量が増えることで基礎代謝が向上する。 |
| 食欲抑制 | 消化吸収に時間がかかるため、満腹感を持続させやすく、過食防止に繋がる。 |
| 食事誘発性熱産生向上 | 体内で熱産生を促し、食事誘発性熱産生を高めることで、消費カロリー増加に貢献する。 |
| 脂肪燃焼効果向上 | 筋肉量の増加により、脂肪燃焼効果を高める。 |
このように、プロテインは、様々なメカニズムを通して減量をサポートします。効果的にプロテインを活用することで、健康的にそして効率的に理想の体型を目指せるでしょう。
2. 減量に最適なプロテインの種類
減量を成功させるためには、適切なプロテインの種類を選ぶことが重要です。それぞれのプロテインの特徴を理解し、自分に合ったものを選びましょう。
2.1 ホエイプロテインの特徴とメリット・デメリット
ホエイプロテインは、牛乳から作られるプロテインで、吸収スピードが速いのが特徴です。トレーニング直後に摂取することで、筋肉の修復と成長を促進します。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 吸収が速い | 乳糖不耐症の方は注意が必要 |
| 必須アミノ酸が豊富 | 価格が比較的高め |
| 種類が豊富で風味も様々 |
ホエイプロテインは、BCAA(分岐鎖アミノ酸)を豊富に含んでおり、筋肉の分解抑制にも効果的です。そのため、減量中でも筋肉量を維持したい方におすすめです。また、様々なフレーバーが販売されているため、飽きずに続けやすいというメリットもあります。
ただし、乳糖不耐症の方は、お腹がゴロゴロするなどの症状が出る可能性があります。その場合は、WPI(ホエイプロテインアイソレート)という乳糖を取り除いたタイプを選ぶと良いでしょう。
2.2 ソイプロテインの特徴とメリット・デメリット
ソイプロテインは大豆を原料としたプロテインで、吸収スピードが緩やかです。腹持ちが良いため、間食の代わりとしてもおすすめです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 腹持ちが良い | 吸収が遅い |
| コレステロール値を下げる効果 | 独特の風味がある |
| イソフラボンが含まれている |
ソイプロテインは大豆イソフラボンを含んでおり、女性ホルモンに似た働きをするため、更年期障害の症状緩和や骨粗鬆症予防にも効果が期待できます。また、コレステロール値を下げる効果もあるため、健康維持にも役立ちます。
ただし、吸収スピードが遅いため、トレーニング直後の摂取にはあまり向いていません。また、独特の風味があるため、好みが分かれる場合もあります。
2.3 カゼインプロテインの特徴とメリット・デメリット
カゼインプロテインも牛乳由来のプロテインですが、ホエイプロテインとは異なり、吸収スピードが非常に遅いです。そのため、就寝前に摂取することで、睡眠中の筋肉の分解を防ぎます。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 吸収が非常に遅い | 価格が比較的高め |
| 腹持ちが非常に良い | |
| 持続的なアミノ酸供給が可能 |
カゼインプロテインは、長時間にわたってアミノ酸を供給し続けるため、筋肉の分解抑制効果が非常に高いです。就寝前の摂取だけでなく、長時間の空腹時にもおすすめです。
ただし、吸収が遅いため、トレーニング直後の摂取には適していません。また、価格が比較的高めであることもデメリットとして挙げられます。
2.4 プロテインの種類の選び方
それぞれのプロテインの特徴を踏まえ、自身の目的やライフスタイルに合わせて最適なプロテインを選びましょう。例えば、トレーニング直後には吸収の速いホエイプロテイン、就寝前には吸収の遅いカゼインプロテイン、間食には腹持ちの良いソイプロテインといったように使い分けるのも効果的です。複数のプロテインを組み合わせて摂取することで、より効率的に減量を進めることができます。
また、プロテインを選ぶ際には、原材料や添加物にも注目しましょう。人工甘味料や香料などが多く含まれているものは避け、できるだけシンプルな成分のものを選ぶように心がけてください。
3. 効果的なプロテインの摂取タイミングと回数
プロテインを摂取するタイミングは、その効果を最大限に引き出す上で非常に重要です。ここでは、減量に効果的なプロテインの摂取タイミングと回数について詳しく解説します。
3.1 トレーニング前後の摂取
トレーニング前後30分以内は、筋肉の分解抑制と合成促進のためにプロテインを摂取するゴールデンタイムと言われています。トレーニングによってダメージを受けた筋肉は、栄養を欲している状態です。このタイミングでプロテインを摂取することで、効率的に筋肉の修復と成長を促すことができます。特に、トレーニング後のプロテイン摂取は重要です。激しい運動の後には、速やかに吸収されるホエイプロテインがおすすめです。
3.2 朝食時の摂取
朝食にプロテインを摂り入れることで、1日のタンパク質摂取量を確保しやすくなります。また、朝食にプロテインを摂取することで、血糖値の急上昇を抑え、満腹感を持続させる効果も期待できます。忙しい朝でも手軽にタンパク質を補給できるため、ダイエット中の朝食におすすめです。ソイプロテインやカゼインプロテインなど、腹持ちの良いプロテインを選ぶと良いでしょう。
3.3 間食としての摂取
間食にプロテインを摂取することで、空腹感を抑え、食べ過ぎを防ぐことができます。また、タンパク質をこまめに摂取することで、筋肉の分解を抑制し、代謝を維持する効果も期待できます。特に、ダイエット中は甘いものや脂っこいものを食べたくなる衝動に駆られがちですが、プロテインを間食に取り入れることで、こうした衝動を抑える助けとなります。個包装のプロテインバーや、水で溶かすだけのプロテインパウダーなどが便利です。
3.4 就寝前の摂取
就寝中は、成長ホルモンが分泌され、筋肉の修復と成長が活発に行われる時間帯です。就寝前にプロテインを摂取することで、睡眠中の筋肉の分解を防ぎ、成長を促進することができます。吸収の遅いカゼインプロテインは、就寝前の摂取に最適です。
3.4.1 就寝前プロテインの効果と注意点
就寝前にプロテインを摂取することで、睡眠中の筋肉の分解抑制、成長ホルモンの分泌促進、翌朝の空腹感の軽減などの効果が期待できます。しかし、胃腸への負担を軽減するために、就寝1~2時間前には摂取を済ませるようにしましょう。また、過剰摂取は消化不良や睡眠の質の低下につながる可能性があるため、適量を守ることが大切です。
| 摂取タイミング | おすすめのプロテインの種類 | 効果 |
|---|---|---|
| トレーニング前 | ホエイプロテイン、EAA | 筋肉の分解抑制 |
| トレーニング後 | ホエイプロテイン | 筋肉の修復と成長促進 |
| 朝食時 | ソイプロテイン、カゼインプロテイン | 1日のタンパク質摂取量の確保、血糖値の急上昇抑制、満腹感の持続 |
| 間食 | ホエイプロテイン、ソイプロテイン、プロテインバー | 空腹感の抑制、食べ過ぎ防止、筋肉の分解抑制 |
| 就寝前 | カゼインプロテイン | 睡眠中の筋肉分解抑制、成長ホルモン分泌促進、翌朝の空腹感軽減 |
上記は一般的な目安であり、個人の体質や生活習慣、トレーニングの強度などによって最適な摂取タイミングや回数は異なります。自分の体に合った摂取方法を見つけることが大切です。
4. 1日の最適なプロテイン摂取量
減量を成功させるためには、プロテインの摂取量を適切に管理することが重要です。多すぎても少なすぎても効果が得られない可能性があります。そこで、この章では、1日の最適なプロテイン摂取量について詳しく解説します。
4.1 減量時の適切なタンパク質量
減量中は、筋肉量を維持しながら体脂肪を減らすことが重要です。そのためには、十分な量のタンパク質を摂取する必要があります。一般的に、体重1kgあたり1.2g~1.6gのタンパク質を摂取することが推奨されています。例えば、体重が60kgの人であれば、1日に72g~96gのタンパク質を摂取するのが目安となります。
ただし、この数値はあくまで目安です。年齢、性別、活動量、体質などによって最適な摂取量は異なります。自身の状況に合わせて調整することが大切です。
4.2 プロテイン以外の食事からのタンパク質摂取
プロテインサプリメントだけでなく、普段の食事からもタンパク質を摂取するように心がけましょう。高タンパク質食品には、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などがあります。これらの食品をバランスよく摂取することで、必要なタンパク質量を確保することができます。
1日に必要なタンパク質量をプロテインサプリメントだけで補おうとすると、過剰摂取になる可能性があります。食事とプロテインサプリメントを組み合わせて摂取することが重要です。
| 食品 | タンパク質含有量(100gあたり) |
|---|---|
| 鶏むね肉(皮なし) | 約23g |
| 鮭 | 約20g |
| 卵(1個) | 約6g |
| 豆腐(絹) | 約5g |
| 納豆(1パック) | 約7g |
| 牛乳(100ml) | 約3g |
| ギリシャヨーグルト(無糖) | 約10g |
上記の表を参考に、普段の食事でどの程度のタンパク質を摂取できているかを確認し、プロテインサプリメントで補う量を調整しましょう。バランスの良い食事を心がけることが、健康的な減量への近道です。
5. プロテイン摂取における注意点
プロテインは減量をサポートしてくれる心強い味方ですが、正しい摂取方法を理解せずに使用すると、期待する効果を得られないばかりか、健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。安全かつ効果的にプロテインを活用するために、以下の注意点にしっかりと目を通しておきましょう。
5.1 過剰摂取のリスク
プロテインはあくまで栄養補助食品です。過剰に摂取すれば、カロリーオーバーとなり体重増加につながる可能性があります。また、腎臓への負担も懸念されます。1日の適切な摂取量を守り、バランスの良い食生活を心がけましょう。
特に、すでに十分なタンパク質を食事から摂取できている場合は、プロテインの追加摂取は必要ありません。過剰摂取による健康被害を防ぐためにも、自身の食生活を振り返り、本当にプロテインが必要かどうかを検討することが大切です。
5.2 アレルギーへの配慮
プロテインには、牛乳由来のホエイプロテイン、大豆由来のソイプロテインなど、様々な種類があります。特定の食品にアレルギーを持つ方は、原材料をよく確認し、アレルギー反応を引き起こす可能性のあるプロテインの摂取は避けましょう。特に、乳製品アレルギーの方はホエイプロテインを、大豆アレルギーの方はソイプロテインを摂取しないように注意が必要です。
初めてプロテインを摂取する際は、少量から試すことをおすすめします。少しでも体に異変を感じた場合は、すぐに摂取を中止し、医師に相談しましょう。
5.3 人工甘味料などの添加物
一部のプロテインには、飲みやすくするために人工甘味料や香料などの添加物が含まれている場合があります。これらの添加物は、体質によっては消化不良や下痢などの症状を引き起こす可能性があります。また、人工甘味料の過剰摂取は健康への影響も懸念されています。
プロテインを選ぶ際には、成分表をよく確認し、添加物の種類や量に注意を払いましょう。特に、人工甘味料に敏感な方は、無添加のプロテインを選ぶことをおすすめします。
| 注意点 | 詳細 | 対策 |
|---|---|---|
| 過剰摂取 | カロリーオーバー、腎臓への負担 | 適切な摂取量を守る、バランスの良い食生活 |
| アレルギー | 原材料由来のアレルギー反応 | 原材料を確認、少量から試す、異変を感じたら摂取中止 |
| 添加物 | 消化不良、下痢、健康への影響 | 成分表を確認、無添加プロテインを選ぶ |
プロテインは正しく摂取すれば、減量を効果的にサポートしてくれる頼もしい存在です。しかし、注意点を守らずに摂取すると、健康を害するリスクも伴います。今回ご紹介した内容を参考に、安全かつ効果的にプロテインを活用し、健康的な減量を目指しましょう。
6. おすすめの減量向けプロテインレシピ
減量中にプロテインを効果的に摂取するためには、味に飽きずに続けられる美味しいレシピを知っておくことが重要です。ここでは、手軽に作れるおすすめの減量向けプロテインレシピをいくつかご紹介します。
6.1 ザバス ホエイプロテイン100を使ったスムージーレシピ
6.1.1 グリーンベリースムージー
野菜と果物の栄養を一緒に摂れるスムージーです。プロテインの甘さとベリーの酸味が相性抜群です。
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| ザバス ホエイプロテイン100(ヨーグルト風味) | 付属スプーン3杯 |
| 冷凍ミックスベリー | 100g |
| ほうれん草 | 30g |
| 水 | 200ml |
すべての材料をミキサーに入れ、滑らかになるまで混ぜれば完成です。
6.1.2 バナナソイスムージー
腹持ちが良いので、朝食や間食にもおすすめです。バナナの甘みでプロテインの風味もまろやかになります。
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| ザバス ホエイプロテイン100(バニラ風味) | 付属スプーン3杯 |
| バナナ | 1本 |
| 無調整豆乳 | 200ml |
すべての材料をミキサーに入れ、滑らかになるまで混ぜれば完成です。
6.2 ウイダー プロテイン効果を高めるアレンジレシピ
6.2.1 プロテインパンケーキ
朝食やトレーニング後の栄養補給に最適なパンケーキです。甘さ控えめなので、お好みでフルーツやジャムを添えても美味しくいただけます。
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| ウイダー マッスルフィットプロテイン(ココア風味) | 付属スプーン3杯 |
| 卵 | 1個 |
| 牛乳 | 大さじ2 |
| ベーキングパウダー | 小さじ1/2 |
すべての材料をボウルに入れ、泡だて器で混ぜ合わせます。フライパンを熱し、生地を流し込んで両面を焼き色がつくまで焼けば完成です。
6.2.2 プロテインヨーグルト
手軽に作れるので、忙しい時にもおすすめです。ヨーグルトの酸味とプロテインの風味がマッチします。お好みでフルーツやナッツをトッピングしても良いでしょう。
| 材料 | 分量 |
|---|---|
| ウイダー ウェイトダウン プロテイン(フルーツミックス風味) | 付属スプーン2杯 |
| 無糖ヨーグルト | 150g |
ヨーグルトにプロテインパウダーを加え、よく混ぜ合わせれば完成です。
これらのレシピはあくまで一例です。自分の好みに合わせて、フルーツや野菜、調味料などを加えてアレンジしてみてください。飽きずに続けられることが、減量成功の鍵です。
7. プロテインと組み合わせる効果的な減量方法
プロテインをただ摂取するだけでは、その効果を最大限に引き出すことはできません。減量を成功させるためには、プロテインと他の要素を効果的に組み合わせることが重要です。ここでは、有酸素運動、筋トレ、食事管理との組み合わせについて解説します。
7.1 有酸素運動との組み合わせ
有酸素運動は、脂肪燃焼を促進し、カロリー消費を高める効果があります。プロテインと組み合わせることで、筋肉の分解を防ぎながら、効率的に体脂肪を減らすことができます。ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を、週に数回、30分程度行うことをおすすめします。
プロテインを摂取するタイミングとしては、有酸素運動の30分~1時間前が効果的です。運動前にプロテインを摂取することで、運動中のエネルギー源として利用され、筋肉の分解を防ぐことができます。また、運動後の疲労回復にも役立ちます。
7.2 筋トレとの組み合わせ
筋トレは、筋肉量を増やし、基礎代謝を高める効果があります。基礎代謝が上がると、何もしていない時でもカロリー消費量が増えるため、太りにくい体質を作ることができます。プロテインと組み合わせることで、筋トレの効果をさらに高めることができます。筋トレを行う日は、特にプロテインの摂取を意識しましょう。
| タイミング | 効果 |
|---|---|
| トレーニング30分~1時間前 | 運動中のエネルギー源となり、筋肉の分解を防ぐ |
| トレーニング直後~30分以内 | 筋肉の修復と成長を促進する |
| 就寝前 | 睡眠中の筋肉の分解を防ぎ、成長ホルモンの分泌を促進する |
7.2.1 筋トレの種類
様々な種類の筋トレがありますが、スクワット、デッドリフト、ベンチプレスなどのBIG3と呼ばれる種目は、多くの筋肉を動員するため、効率的に筋肉量を増やすことができます。これらの種目を中心に取り入れることをおすすめします。自重トレーニングでも効果は期待できますが、負荷を徐々に上げていくことが重要です。
7.3 食事管理との組み合わせ
プロテインはあくまで補助的な役割であり、食事管理が減量のベースとなります。バランスの良い食事を心がけ、タンパク質、炭水化物、脂質を適切な割合で摂取することが重要です。
| 栄養素 | 役割 | 摂取目安 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 筋肉の構成成分。筋肉の維持・増加に必要。 | 体重1kgあたり1.2g~1.6g |
| 炭水化物 | エネルギー源。不足すると疲労感や集中力の低下につながる。 | 総摂取カロリーの50~60% |
| 脂質 | ホルモンの生成や細胞膜の構成に必要。 | 総摂取カロリーの20~30% |
過度な糖質制限や脂質制限は、健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、避けましょう。栄養バランスの良い食事を心がけることで、健康的に減量することができます。
これらの方法を組み合わせることで、プロテインの効果を最大限に引き出し、効率的に減量を進めることができます。自分のライフスタイルや目的に合わせて、最適な方法を選びましょう。
8. よくある質問
プロテインに関する様々な疑問にお答えします。
8.1 プロテインを飲むと太るってホント?
プロテインはあくまでタンパク質を効率的に摂取するためのサプリメントです。摂取カロリーが消費カロリーを上回れば、体重は増加します。プロテイン自体に脂肪を蓄積させる特別な作用はありません。むしろ、プロテインは筋肉の合成を促進し、基礎代謝を高める効果が期待できます。基礎代謝が上がれば、消費カロリーも増えるため、結果的に太りにくい体質へと変化していきます。ただし、過剰に摂取すればカロリーオーバーになるため、摂取量には注意が必要です。1日の総摂取カロリーをコントロールしながら、適切な量のプロテインを摂取するようにしましょう。
8.2 女性でもプロテインを飲んでも大丈夫?
はい、女性でも安心してプロテインを飲むことができます。プロテインは筋肉の材料となるタンパク質を効率的に補給するためのものです。ダイエットや美容、健康維持のためにプロテインを活用する女性は多くいらっしゃいます。女性ホルモンの影響で男性に比べて筋肉がつきにくい女性にとって、プロテインは効率的にタンパク質を摂取する有効な手段となります。特に、ダイエット中は食事制限によってタンパク質が不足しがちです。プロテインでタンパク質を補うことで、筋肉量の減少を防ぎ、リバウンドしにくい体作りをサポートします。また、肌や髪、爪の健康維持にもタンパク質は欠かせません。
8.3 プロテインを飲むとお腹を壊すのはなぜ?
プロテインを飲んでお腹を壊す原因はいくつか考えられます。主な原因としては、乳糖不耐症、プロテインに含まれる人工甘味料、一度に大量に摂取することなどが挙げられます。
| 原因 | 症状と対策 |
|---|---|
| 乳糖不耐症 | 牛乳に含まれる乳糖を分解する酵素が不足しているために、下痢や腹痛などの症状が現れます。ホエイプロテインは牛乳由来のため、乳糖不耐症の方は注意が必要です。乳糖を含まないソイプロテインやカゼインプロテインを選ぶ、もしくはWPI(ホエイプロテインアイソレート)のような乳糖含有量の少ないプロテインを選ぶと良いでしょう。 |
| 人工甘味料 | 一部のプロテインに含まれる人工甘味料が、お腹の調子を崩す原因となることがあります。人工甘味料不使用のプロテインを選ぶ、もしくは摂取量を調整することで改善される可能性があります。 |
| 一度に大量摂取 | 一度に大量のプロテインを摂取すると、消化吸収が追いつかず、お腹の不調につながることがあります。少量ずつこまめに摂取する、水や牛乳でしっかりと溶かしてから飲むように心がけましょう。 |
| その他 | プロテインの種類によっては、お腹がゆるくなる成分が含まれている場合があります。自分に合ったプロテインを見つけることが大切です。様々な種類を試してみて、お腹の調子に変化がないか確認しましょう。 |
9. まとめ
減量を成功させるためには、プロテインを正しく活用することが重要です。この記事では、プロテインが減量に効果的なメカニズムから、種類ごとの特徴、効果的な摂取タイミング、摂取量、注意点、そして具体的なレシピまで、幅広く解説しました。プロテインはあくまで補助的な役割であり、食事管理や運動と組み合わせることで、より効果的に減量を実現できます。
特に、ホエイプロテインは吸収が早くトレーニング後におすすめ、ソイプロテインは大豆由来で腹持ちが良い、カゼインプロテインはゆっくり吸収されるため就寝前におすすめ、といったように、それぞれの特徴を理解して選ぶことが大切です。自分のライフスタイルや目的に合ったプロテインを選び、適切なタイミングと量で摂取することで、健康的に減量を進めましょう。過剰摂取は体に負担をかける可能性があるため、1日の摂取量を守り、バランスの良い食事を心がけてください。また、プロテインの種類によってはアレルギー反応が出る可能性もあるため、注意が必要です。
プロテインを効果的に活用し、理想の体型を目指しましょう。この記事が、あなたの減量の一助となれば幸いです。お悩みの方は当院へご相談ください。
店舗情報
-
店舗名
- 緑の杜整体院
-
代表
- 下田 高裕
-
住所
- 〒861-1112
熊本県合志市幾久富1909-247
駐車場あり
地図を見る -
営業時間
- 火曜~土曜10:00~20:00
日曜10:00~12:00
詳細はこちら -
休診日
- 月曜・日曜の午後
-
アクセス
- 光の森から車で8分
-
TEL
-
096-274-4976
施術中でお電話に出られないことがあります。
留守番電話に「お名前」「お電話番号」をお残しください。
こちらから折り返しご連絡させていただきます。
営業時間
緑の杜整体院は 「 当日予約OK 」 です。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00〜12:00 | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12:00〜20:00 | 休 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 休 | ◯ |